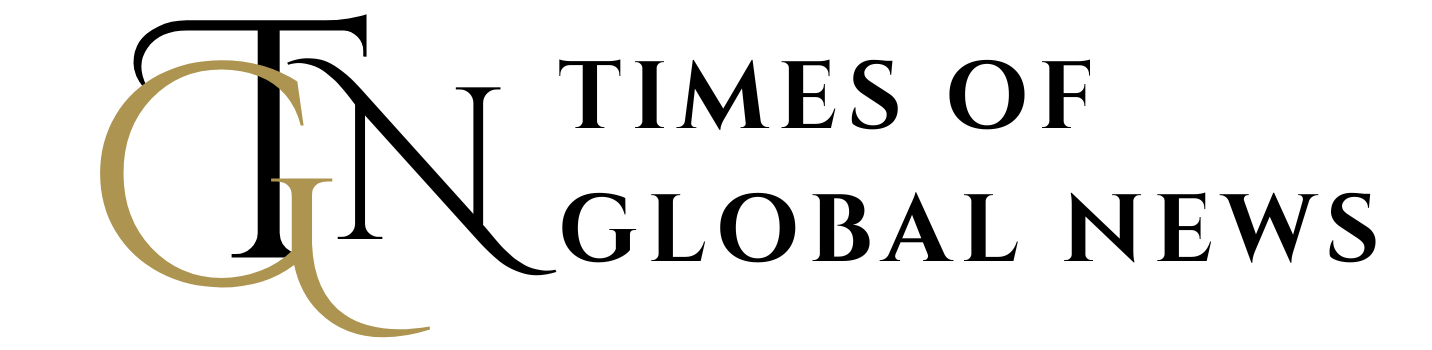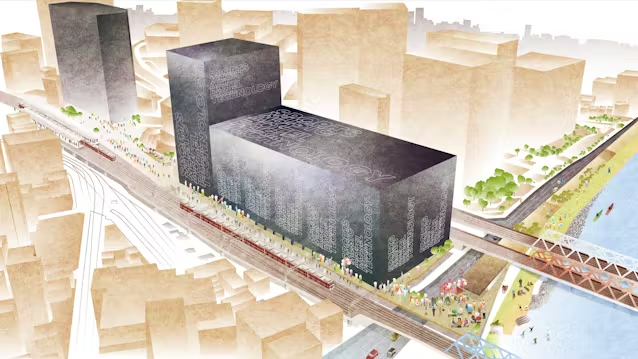紬織 の人間国宝で文化勲章受章者の志村ふくみさんが9月に100歳を迎えた。一貫して草木染にこだわり、故郷の琵琶湖沿岸の風景や古典文学、時には現代アートや音楽にも想を得て、自らの内面を織物に昇華させた作品の世界は、若い世代にもファンが多い。その源泉をたどる記念の展覧会が、東京都港区の大倉集古館で開催中だ。随筆の名手としても知られ、自然と人間との関わりや日本文化について深く考察してきた志村さん。激動の「1世紀」を生き抜き、その先にどんな風景を見ているのだろうか。
写経、和歌に親しむ日々――失われゆく日本の自然・手仕事の文化に危機感も
「もう、100歳ですよ」。京都・嵯峨野に10月上旬、「百寿」を迎えたばかりの志村さんを約3年ぶりに訪ねると、晴れやかな笑顔で迎えてくれた。生き生きとした表情、張りのある声が変わっていないことに驚きを覚えるとともに、 安堵 した。

志村さんは1924年、滋賀・近江八幡生まれ。東京から戻って離婚を決意した31歳の頃、母の手ほどきを受けて織物を始め、かつて農家の女性の普段着とされた紬織を芸術の域に高めた。現在は般若心経の写経を日課とし、和歌の本を読んだり、軽い体操をしたり。娘で染織家の洋子さんによると、着物や帯のデザインを色鉛筆で描き、工房で織り上げた作品や草木染の糸を手に取って意見を交わすこともあるという。
梅や桜の枝、紅花、 茜 、ヨモギ……。志村さんは平安時代の面影を残し豊かな自然に囲まれた嵯峨野に工房を構え、様々な植物染料で絹糸を染めることを「命の色をいただく」と表現してきた。近年は身近な自然が失われゆく状況を憂えるとともに、加速する着物の文化や手仕事の衰退への危機感も強い。11月まで滋賀県立美術館で開かれた回顧展に志村さんは、「私の生きた一世紀と、次の一世紀を思うと(環境の変化に) 慄然 とする」という所感を寄せた。「着物は日本人の魂というのが持論ね」と洋子さんが語りかけると志村さんはうなずき、「私は(本にも)そう書いています」と強調した。
米寿を過ぎても高い創作意欲、国内外の文学・美術にも触発

志村さんの京都の工房に筆者が通い、長時間のインタビューを重ねたのは2012年秋から13年春にかけてのことだ。読売新聞朝刊の長期シリーズ「時代の証言者」でその歩みをたどり、計20回余りの連載(「染めと織り 志村ふくみ」として後に書籍化)にまとめた。取材期間中に米寿を迎えた志村さんは、工房で弟子たちとともに絹糸を染め、ほぼ毎日、機に向かって精力的に作品を生み出していた。 凜 としていながら、たおやかなたたずまいの中に、創作への意欲がほとばしるようなエネルギーを感じた。
今回、大倉集古館に展示されている着物の製作年を見ると、2012年~14年前後の作品が目に付く。30歳代に入って織物を始めてから、染織家としていくつも作ってきたピークの一つが、米寿の頃から90歳にかけてあったのは驚異的なことだと思う。

たとえば、長年作品を愛読してきたオーストリアの詩人、リルケへの憧れを春の野草の繊細な色彩で表現した「柳の国」(2012年)、リルケ作品から名付けた重厚な「悲歌」(同)。この頃、志村さんはリルケの作品について思いをつづった書籍も 上梓 している。
可憐 なピンクの格子柄が印象的な「舞姫」も2013年の作で、工房で蚕から取った透明感のある糸、 生絹 を紅花で染めて織ったという。この頃、志村さんは水俣病を描いた作家、石牟礼道子さん(2018年に死去)の新作能「沖宮」の上演に向けて衣装の監修を依頼されていた。主人公の少女の衣装に石牟礼さんが所望したのが鮮やかな紅色で、「舞姫」については「まず(紅花で)1作をこころみた」と志村さんは作品集に記している。
石牟礼さんとの交流は、東日本大震災を契機に一段と深まり、人間と自然の関係に対する2人の深い憂慮は、魂が響き合うような往復書簡に結実した。
志村さんが娘の洋子さんと染織の学校「アルスシムラ」を2013年に開校した背景にも、震災により自然と手仕事の未来に強い危機感を覚えたことがあったようだ。この頃の志村さんの原動力の一つに、震災と原発事故による衝撃があったのだろう。
その一方で、90歳を目前にした染織家の自由な発想力も際だっている。お気に入りのジャズのCDカバーに触発されて織り始めたが、完成に近づくと一遍上人の「聖絵」が浮かんできたという「諸国遊行」(2014年)、ベートーベンのバイオリン・ソナタを題材に、リズミカルな格子柄に躍動感がある「クロイツェル・ソナタ」(2013年)――。
東京で100歳記念の回顧展 12月17日から後期展示
志村さんの100歳記念の回顧展は10~11月に滋賀県立美術館でも開かれ、主に同館所蔵の作品が並んだ。大倉集古館の展示はその巡回展ではなく、志村さんが手元に残してきた着物を中心に個人蔵の作品約60点(前期、後期=12月17日~2025年1月19日=で入れ替え)を集めている。

展示室に入ると、まず目に入るのは1950年代、織物を始めた最初期に製作した帯や、母・小野豊が手がけた着物などで、貴重な作品が並ぶ。初めて自作した着物「秋霞」は、かつて農家の女性らが糸を惜しんで作った「つなぎ糸」を濃紺の地に差し入れるように織り上げた記念碑的な作品で、日本伝統工芸展に入賞した。志村さんに織物を勧めた思想家、柳宗悦の民芸運動の影響を感じさせる初期の作品はどこか質実な雰囲気が漂う。京都に工房を構えた40歳代半ばからは独自の作風を確立し、扱う植物染料の幅も広がって作風も多彩になっていったことが伝わってくる。
「第五、第六の季節を生きる」透徹したまなざしと次世代への思い

志村さんはかつて、随筆に「第五の季節を生きている」とつづった。人生の四季を超えた「厳冬期」を迎えているのだと。米寿の頃のインタビューでも「今は第六の季節でしょうか。すでに自分の中には、何割もの『死』が入っている。その現実を受け止め、残りの生を、どうやって一日一日を生きていくか」と話していた。

たゆみなく織物の道を歩んできた志村さんは80歳を前に初めての「スランプ」に陥り、染織から遠ざかったことがある。「二度と機の前に座ることはない」と思っていたというが、その間に端布によるオブジェの製作などの新境地を開き、2年余り後に「復活」。ライフワークの琵琶湖を題材にした「湖水シリーズ」の新作、優美な色遣いで表現した源氏物語の連作などを次々に生み出した。今回の展示にはその頃の作品も目立つ。
さらに米寿の前後は作品制作に打ち込む傍ら、国内外での展覧会や講演などで多忙を極めていった。充実した日々の中でも、志村さんは自らを「厳冬期にある」ととらえる透徹したまなざしを持ち続けていたのではないかと思う。その一方で、常に工房で若い弟子たちとともに仕事をすることを大事にし、「いつもどんな色に染まるか、ワクワクする」というみずみずしい感性を持ち続けてきた。
深い思い入れのある染織の学校「アルスシムラ」には、洋子さんや孫の昌司さん、宏さんらの尽力もあり、10年余りで約500人が学び、織物を本格的に志す若い世代も育っている。着物離れが進む中、容易な道ではないが、志村さんにとって大きな喜びだ。
100歳を機に「若い人へのメッセージ」を求めたところ、「誘惑の多い時代ですが、自分の精神を大事にしてほしい」と力強い言葉が返ってきた。
日本の豊かな自然と手仕事に込められた先人の思いを尊び、次世代につなげたいという志村さんの願いは、作品を通じて幅広い世代の胸に届くだろう。